ブログ
インフルエンザ予防接種は福利厚生にできる?接種率を上げるコツを解説

「従業員にインフルエンザ予防接種を受けてもらいたいけれど、福利厚生にすることはできるのだろうか?」「インフルエンザ予防接種率を上げるにはどうすればよいのだろうか?」と悩んでいませんか?
今回は、インフルエンザ予防接種は福利厚生になるのかについて解説します。この記事では、インフルエンザ予防接種率を上げる方法までご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
インフルエンザ予防接種は福利厚生になる?
インフルエンザ予防接種を福利厚生にできます。
インフルエンザ予防接種は健康保険の対象とならず実費で受けることになります。医療機関によりインフルエンザ予防接種費用は異なりますが、一般的に3,000〜5,000円です。これらの費用を会社が負担してあげれば、従業員にインフルエンザ予防接種を受けてもらいやすくなります。
インフルエンザ発症後の休職期間は、発症後5日間、解熱後2日が経過するまでとされています。最低でも5日間休んで安静にしなければなりません。
「インフルエンザを発症したくないから」「うつしたくないから」という理由でインフルエンザ予防接種を受けたいという方はいます。そのため、インフルエンザ予防接種を福利厚生にすれば喜ばれるでしょう。
インフルエンザ予防接種を福利厚生にする際のポイント

インフルエンザ予防接種を福利厚生にする際のポイントは4つあります。
従業員に平等に機会を提供する
福利厚生はすべての従業員が平等に利用できることが原則です。特定の部署や特定の立場の人のみ利用できる福利厚生は認められていません。
例えば、役職者、営業職のみなどにインフルエンザ予防接種する場合は福利厚生として認められません。そのため全従業員を対象としましょう。
妥当な金額を支給する
福利厚生は社会通念上、妥当な金額であれば認められます。あまりにも高額ものは福利厚生費として認められません。また、現金支給は認められていません。
従業員から領収書を受け取った後に清算します。 医療機関によりインフルエンザ予防接種費用は異なりますが、一般的に3,000〜5,000円です。この相場を参考に一部または全額を負担してあげましょう。
(※社会通念上、従業員の家族の接種費用まで負担するのは認められていません。)
インフルエンザ予防接種を強制してはいけない
インフルエンザ予防接種を福利厚生にしたことを理由に接種を強制してはいけません。
インフルエンザ予防接種では「赤み」「腫れ」「痛み」「発熱」「頭痛」「倦怠感」などの副反応があります。また、心臓病や腎臓病など病気の治療を受けていて、医師から予防接種を受けない方がよいと言われている人もいます。
さまざまな事情がいることを理解した上で、インフルエンザ予防接種は任意とし、従業員の意向を尊重するようにしましょう。
ンフルエンザ予防接種方法を考える
インフルエンザ予防接種方法は2通りあります。
予防接種の費用を負担する インフルエンザ予防接種の費用を負担する形であれば、個人の意向を尊重しやすくなります。インフルエンザ予防接種の領収書をもらい経費精算してあげてください。
事業内接種を実施する 事業内接種を実施すれば、インフルエンザ予防接種の予約などせずに済みます。そのため、インフルエンザ予防接種を受けたくても仕事が忙しい方に喜ばれるでしょう。
しかし、インフルエンザの予防接種を受けたくない方が肩身の狭い思いをしてしまいます。そのため、事業内接種を実施する際は、あくまで個人の自由、意志を尊重する旨を伝えてあげてください。
インフルエンザ予防接種の福利厚生を利用してもらう方法

予防接種を受けやすい環境をつくる
インフルエンザ予防接種を打ちたい方は多くいますが、若手社員などは周囲の様子を見て予防接種を受けるかどうか判断します。
インフルエンザ予防接種を受ける際には業務を止めなければならず、周囲に迷惑をかけてしまいます。そのため、インフルエンザ予防接種を受けたいと言えない方もいるでしょう。 そのため、役員や上司がインフルエンザ予防接種を受けて予防接種を受けやすい環境を作ってあげましょう。
予防接種を受けるための特別休暇や早退・中抜けなどを許可すると、インフルエンザ予防接種率を上げられます。
健康意識を高める
従業員の健康意識を高めることができれば、インフルエンザの予防接種率を上げられます。
例えば、インフルエンザ予防接種の福利厚生があることを周知するためにメールを配信しましょう。その際に、インフルエンザに感染するリスクなどを伝えると接種率が上げられます。
社内でラジオ体操したりスポーツイベントを開催するのも効果的です。
申請アプリを用意しておく
インフルエンザ予防接種の申請アプリを作成しておけば、申請・精算が楽になります。
(1)予防接種の費用を負担する
予防接種の費用を負担する場合は、病院の領収書を渡してもらう必要があります。証憑書類(領収書)を電子保管しておくことで、福利厚生費として認められて非課税の取り扱いを受けられるようになります。
(2) 事業内接種を実施する
事業内接種を実施する場合は、受けるか受けないかをアンケートを事前に取ることができます。オンライン上で手続きが完了するため、インフルエンザ予防接種を受けたくない旨を伝えやすくなります。
インフルエンザ予防接種は福利厚生で経費計上できる
インフルエンザ予防接種は、次の条件を満たした場合は福利厚生としてみなされて、非課税の取り扱いを受けられます。
- 従業員に平等に機会を提供する 社会通念上妥当な金額である
- 従業員のインフルエンザ予防接種代金である
- 証憑書類(領収書)を電子保管する
上記の条件を満たさない場合は、福利厚生としてみなされず課税対象となります。
インフルエンザ予防接種を福利厚生で導入している企業事例
インフルエンザ予防接種を福利厚生で導入している企業では、どれぐらいの金額を支給しているのでしょうか?どのようにインフルエンザ予防接種率を上げているのでしょうか?ここでは、企業の取り組み事例をご紹介します。
三和建設株式会社
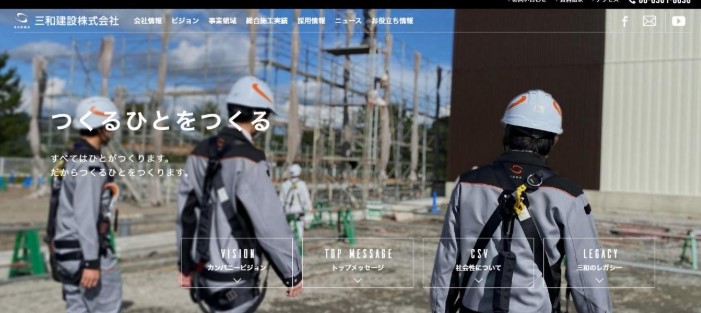
出典:『三和建設株式会社』
三和建設株式会社は2017年からインフルエンザ予防接種費用の一部を補助し、従業員の健康増進に努めてきました。
2019年から近隣のクリニックと連携し、従業員がスムーズにインフルエンザ予防接種が打てる体制づくりを整えて接種率を上げています。 また、従業員の健康意識を高めるためのさまざまな取り組みを実施し、健康を意識し合う職場づくりをしています。
ローム株式会社

出典元:『ローム株式会社』
ローム株式会社は、健康経営優良法人に7年連続認定されている企業です。
従業員の健康増進のために、肩こり・腰痛予防のオンラインセミナーやスポーツイベントを開催。また、希望者に対しては「風疹抗体検査」「婦人科検診」「インフルエンザ予防接種」の機会を無償で提供しています。
日頃から健康増進のイベントを実施しているため、約9割の方が検査や予防接種を受けています。
NTTアドバンステクノロジ株式会社
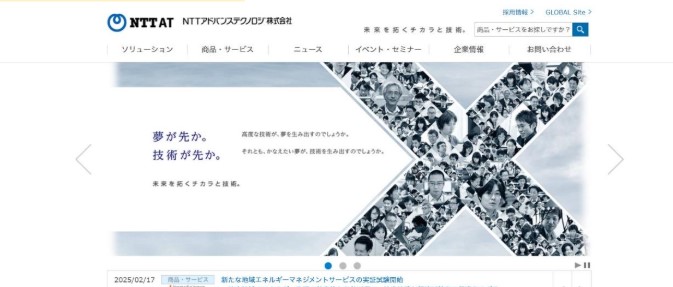
出典元:『NTTアドバンステクノロジ株式会社』
NTTアドバンステクノロジ株式会社は、健康経営推進宣言をしています。
<健康経営推進宣言>
社員の健康保持・増進に積極的に取り組み、健康づくりをサポートします。 社員は自らの健康づくりのための行動と努力を続けます。 全社員が一丸となり活き活きとした職場環境づくりに取り組みます。 1人でも多くの方にインフルエンザ予防接種を受けてもらうために出張接種を実施しています。
医療機関に各事業所に出張してもらい、事業内接種の機会を設けることで仕事が忙しい方もインフルエンザ予防接種が受けられるように配慮していることが大きな特徴です。
事業内接種だけではなく、別の医療機関の予防接種を受けることも可能とし、特別休暇や早退・中抜けを認めることで接種率を上げています。
まとめ
インフルエンザ予防接種を福利厚生にできます。非課税の取り扱いにするためには、次の条件を満たしましょう。
- 従業員に平等に機会を提供する
- 社会通念上妥当な金額である
- 従業員のインフルエンザ予防接種代金である
- 証憑書類(領収書)を電子保管する
インフルエンザ予防接種の申請アプリを作成しておけば、申請・精算が楽になります。申請の負担が少ないほど、福利厚生は利用されやすくなります。そのため、福利厚生の利用率を上げたい方は申請アプリを作成してみてください。
consentFlowであれば、さまざまなアプリを数分で簡単に作成できます。プロコードを扱えば、アプリをカスタマイズすることもできます。無料のデモ体験を提供しているため、申請アプリを作成してみてください。
